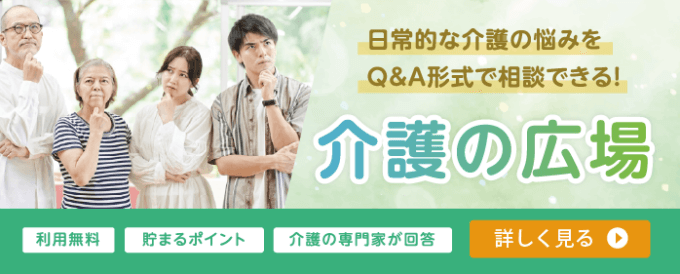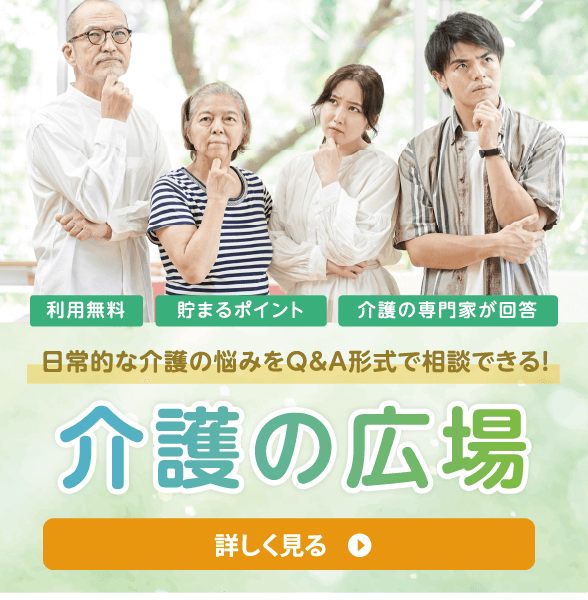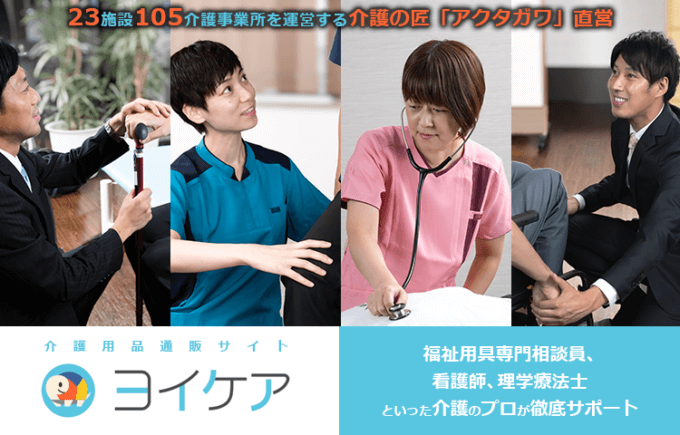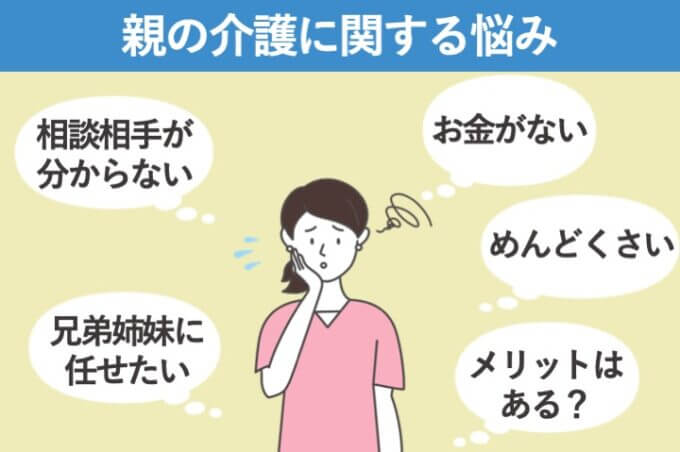在宅介護をされている方の多くは、介護サービスに詳しくない人がほとんどです。実際に訪問介護を利用すると、どんなサービスをしてくれるのか気になるところです。特に、医療行為が必要なご家庭では不安もあるでしょう。今回は訪問介護でヘルパーが介護サービス内でできる医療行為の可不可についてご紹介します。
・白内障の目薬を差してもらえるのか
・定期的にたんの吸引をしてもらえるのか
・呼吸が苦しいときに血中酸素濃度を測ってくれるのか
軽微なケガの対応だけではなく、万が一の救命措置についても記述してあります。ぜひ最後までご覧ください。
目次
介護ヘルパーに頼めること頼めないこと

訪問介護のヘルパーは、介護保険制度によって援助の「できること」と「できないこと」に分けられています。原則としてヘルパーは医療行為ができませんが、専門的な判断が必要ではない場合に限って「研修を受けた介護士が一定の医療行為」ができるように法改正がされました。また「医療的ケア」の対応は問題なく対応できます。以下、詳しく解説します。
擦り傷、切り傷の処置は頼めるか
擦り傷、切り傷などの軽微なケガに対する処置は「医療的ケア」としてヘルパーに頼めます。具体的には絆創膏や汚れたガーゼの交換、やけどの対応など、常識の範囲内の応急処置が可能ですが、床ずれのような傷口の洗浄・薬の塗布などの処置は「医療行為」でありヘルパーは対応できません。医療行為か否かは「専門的なケアの必要性の有無」が判断の目安になります。
目薬をさしてもらうことは頼めるか
点眼薬を差すことはできます。ですが、医師から指示されていない目薬の介助は、ヘルパーの判断で使用の有無は決められないため、要介護者が希望したとしても行えません。また、薬に関連して、一包化された薬の服用の介助、点鼻薬の噴霧、市販の浣腸、座薬の挿入はできます。
熱を測ることは頼めるか
体調不良時やコロナ禍における、日常的な検温はヘルパーが対応できます。わきの下で熱を測る・自動血圧測定器で血圧測定は、医療行為ではなく医療的ケアになります。ですが、介護士が扱えるのは電子機器のみであり、水銀血圧計による血圧測定はできません。検温の結果、もし熱発されていた場合だったとしても、ヘルパーの判断で薬を追加したり減らしたりはできず、医師などの指示が必要になります。
血中酸素濃度の測定は頼めるか
パルスオキシメーターの装着は医療行為ではないので、ヘルパーが対応できます。昨今のコロナ禍では、血中酸素濃度の測定などの体調管理は重要になっていますが、要介護者が普段と様子が違うときは、ヘルパーがバイタルチェックできますのでご安心ください。自治体によってはパルスオキシメーターの購入の補助がある場合がありますので、お近くの役場に確認するといいでしょう。
たんの吸引は頼めるか
たんの吸引は医療行為に該当しますが、要介護者や家族の同意・看護師などの監督下・研修の受講などの条件を満たすことで、介護士がたんの吸引を実施できます。たんの吸引は介護事業所が「喀痰吸引等登録認定行為事業者」の登録が必要なため、医療ケアが必要であれば、対応可能な事業所を探す必要があります。また、原則として家族でも医療行為は認められていませんが、一定の条件で要介護者へのたんの吸引が実施できます。吸引機は介護保険適用外なので、購入の必要はあるものの、各医療メーカーが販売しているので、豊富な種類から探せます。
インスリン注射を打つことは頼めるか
ヘルパーはインスリン注射ができませんが、要介護者やご家族が注射を打つのであれば問題ありません。注射はできないものの、インスリンに関わる準備や補助は介護士が行えます。例えば、インスリン注射を忘れないように声かけ・注射器を渡す・測定結果を一緒に確認・使用済みの注射器を処分などできます。看護師と違い、介護士は準備しかできないものの、確実に注射をできるように見守り・補助も重要な役割です。
尿路カテーテルの装着は頼めるか
尿路カテーテルの装着も医療行為に該当するため、ヘルパーは実施できません。排泄に関連して、肌に圧着したパウチの取り換えも医療行為に相当します。ですが、インスリン注射と同じように補助に関する行為はできるため、ヘルパーはカテーテルの準備や自己導尿補助、体位保持、尿路カテーテルに接続している尿バックの破棄や、ストマの排せつ物の除去など、要介護者が安全確保や動作の見守りをしてくれます。尿路カテーテルは医師などから指導を受けた本人やご家族様が装着できますので、同居される方が具体的な対応手順を学ぶといいでしょう。
呼吸困難に陥った場合、人工呼吸は頼めるか
呼吸困難などによる人工呼吸は緊急対応として対応できますが、人工呼吸は感染症などの持病がない場合に限ります。呼吸困難は主に食事中に起こりますが、ヘルパーは誤嚥による窒息が起こると、背中を叩く、吸引、気道の確保をします。事業所によっては消防署を招いた救命講習を受講しており、容体の急変や、緊急事態では119番通報を行い、AED手配と使用、胸骨圧迫などの救命措置ができます。常にヘルパーがいるとは限らないため、同居するご家族も自治体などで開催している救命講習を受講すると安心です。
ヘルパーに頼める医療行為を知っておこう

ここまで、訪問介護でよくあるヘルパーができる医療行為などをお伝えしました。要点を以下にまとめます。
・ヘルパーは医療的ケアの実施ができる
・たんの吸引などの医療行為は条件付きでできる
・インスリンの注射はできないが、準備、片付けなどはできる
・カテーテルの装着もできないが、補助、体位保持はできる
・緊急時は人工呼吸・AEDの操作などの救命措置はできる
訪問介護は身体・生活介護が中心です。医療行為が必要であれば、事業所や担当のケアマネジャーに相談して、適切なケアについて相談するといいでしょう。ヘルパーは医療行為を行えませんが、ケアを受ける本人やご家族は医師の指導を受ければ対応できます。たんの吸引に限らず、身近なことで高齢者の命を脅かす可能性があるため、医師や看護師などからしっかりとした医療の知識を身につけて、安全な在宅介護をお願いします。これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました。
「訪問介護で介護ヘルパーに頼めること、頼めないこと|医療に関わる行為編」に関連する記事
多くの介護事業所の管理者を歴任。小規模多機能・夜間対応型訪問介護などの立ち上げに携わり、特定施設やサ高住の施設長も務めた。社会保険労務士試験にも合格し、介護保険をはじめ社会保険全般に専門知識を有する。現在は、介護保険のコンプライアンス部門の責任者として、活躍中。