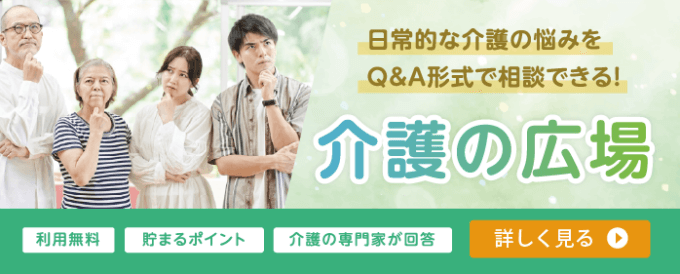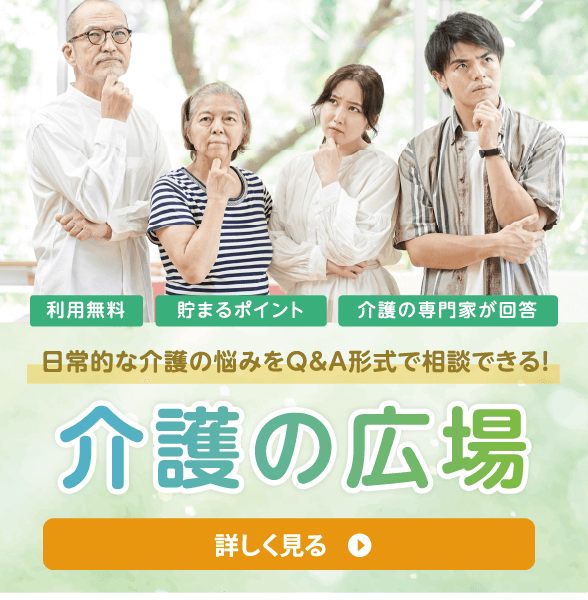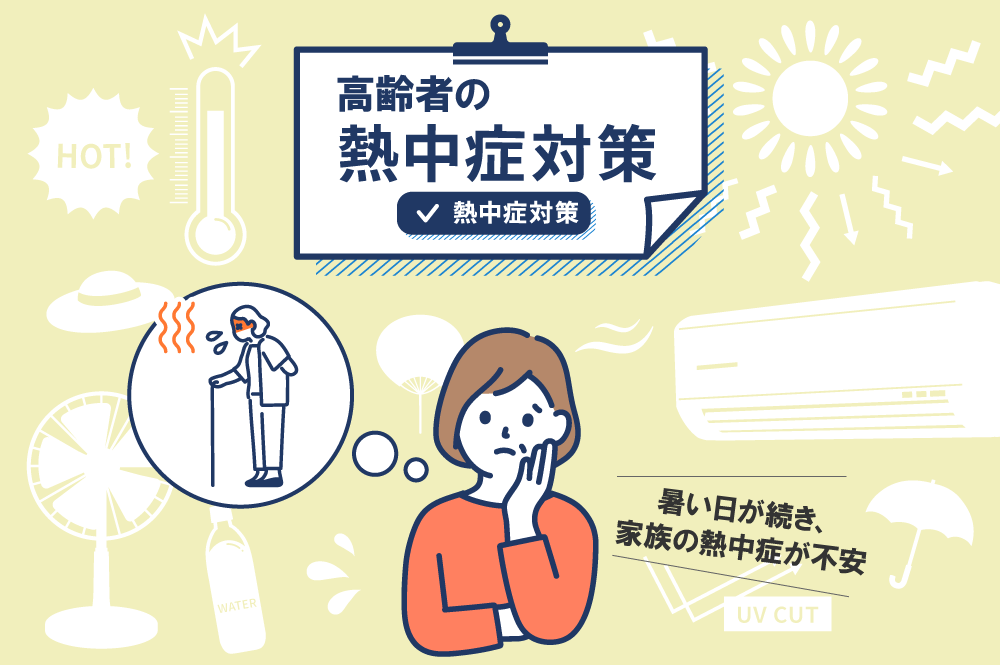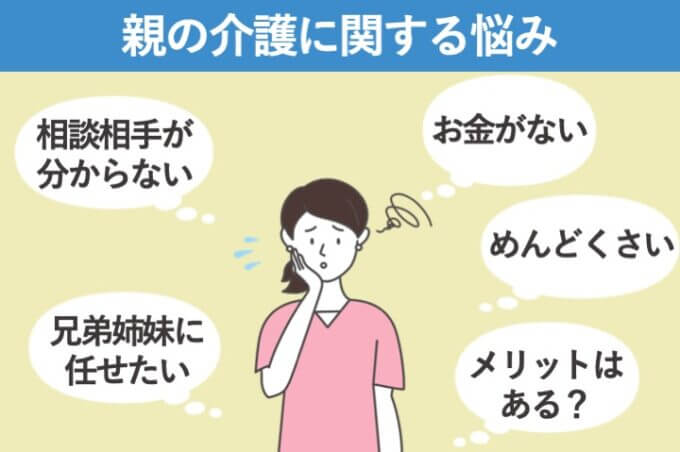高齢者が入所する施設は、介護保険制度上の「施設サービス」に分類される介護保険施設と、有料老人ホームのように民間が運営する施設の2種類に分かれます。介護保険施設は2022年時点で4種類あるので、それぞれの違いや役割を知っておくと施設選びに役立ちます。こちらの記事では、介護保険施設の目的や費用、サービス内容について分かりやすく解説していきます。
目次
介護保険施設ってどんなところ?

要介護高齢者が入所する介護保険施設とは、どのようなところなのでしょうか?定義や特徴、種類について詳しく見ていきましょう。
介護保険施設とは
高齢者が老人ホームのような入所施設を利用すると、介護にかかった費用と居住に関する費用が発生します。介護保険施設とは、介護保険サービスで介護にかかった費用をまかなえる公的施設です。介護保険サービスとは、要介護・要支援の認定を受けた方が利用できる制度のことです。1割から3割の自己負担額で、在宅生活や入居生活を支援するための介護サービスを利用できるのです。介護保険施設は入居時の初期費用が不要で、民間の施設と比べると安価で利用できるという特徴があります。しかしその反面入居待機者が多く、特に特別養護老人ホームは、基本的にすぐ入居できないのが難点です。
介護保険施設は4つの種類に分けられる
| 施設 | 入居対象者 | 特徴 | 医療ケア | 見取り |
| 特別養護老人ホーム | 原則要介護3以上 | 生活の場としての意味合いが強い施設 | △ | 〇 |
| 介護老人保健施設 | 要介護1~5 | リハビリをして在宅復帰を目指すための施設 | 〇 | △ |
| 介護療養型医療施設 | 要介護1~5 | 医療のケアが手厚く、療養施設としても十分な役割を果たす施設 | 〇 | 〇 |
| 介護医療院 | 要介護1~5 | 〇 | 〇 |
介護保険施設は、利用目的によって「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」「介護医療院」の4種類に分かれます。いずれも要介護認定を受けた65歳以上の方が対象で、厚生労働省が定める16の特定疾病よって要介護状態となった40~64歳の方(第2号被保険者)が対象です。それぞれ入居できる期間や費用が異なるため、違いを把握したうえで、要介護者の意向や心身状況・経済状況に応じた施設を選ぶようにしましょう。
特別養護老人ホーム(特養)・ミニ特養

特別養護老人ホーム(通称:特養)は、介護保険上「介護老人福祉施設」として「施設サービス」に分類されている大規模な入所施設です。定員29名以下の小規模な特養については別途「地域密着型サービス」の「地域密着型介護老人福祉施設(通称:ミニ特養)として制度化され、特別養護老人ホームと同等の取り扱いになっています。設置主体は地方公共団体または社会福祉法人であり、入居者数に応じた医師の配置が義務付けられています。
特別養護老人ホームは、介護保険施設の中でも安い費用で利用できることが特徴です。所得が少ない方であれば、負担軽減制度を利用することもできます。食事や入浴、排せつ介助といった日常的な介護のほか、自室の掃除、機能訓練やレクリエーションなど、多様な生活支援サービスを受けられることもポイントです。
一方で、全国的に待機者が多く、申し込んでから入所が決まるまで年単位で待つ場合もあります。
入居条件・入居対象者
特別養護老人ホームは、原則要介護度3以上で自宅での介護が困難な方が入居の対象です。しかし要介護1や要介護2の人でも、特別養護老人ホーム以外での生活が困難と認められる場合は特例的に入居申し込みを受け付けることが可能になっています。
入居の順番は申し込んだ順番ではなく、要介護度をベースにした介護の必要性の度合い・介護者や生活状況・虐待被害の有無その他緊急性などを総合的に判断したうえで優先順位を決めています。
特養の居室タイプは4種類
特養は、他の介護施設に比べて、「住まい」としての性格が強いです。個室については、1人あたりの床面積は10.65㎡以上、多床室の定員は4人以下など基準があります。
特養の居室タイプは、「従来型個室」「多床室」「ユニット型個室」「ユニット型個室的多床室」の4種類です。
従来型個室
居室は個室で、一本の廊下に居室が並んでいるイメージの形態です。食堂やキッチン、浴室などは大勢で使う従来のスタイルです。食堂や浴室への距離が遠い部屋もあります。
多床室
従来の特養に多いタイプで、1部屋4人以下のベッドが置かれた相部屋です。入居者は寂しくない反面、ベッドを仕切るのはカーテン程度であり、プライバシーの保護や感染症対策が課題です。
ユニット型個室
10人程度の入居者を「ユニット」と呼ばれる小グループに分けた構造です。食堂やキッチン、リビングなどの共有スペースを中心に居室が配置されていて、全て個室(6~8畳)です。トイレや洗面所は個室内にある場合と、共有している場合があります。
ユニット型個室的多床室
「ユニット型個室」と同様の施設構造ですが、入居者の居室内の構造が異なります。多床室を可動しない壁などで仕切り、個室に準じた造りにしたものになっています。固定壁の天井部分などに隙間があるので完全な個室にはなっていません。
介護老人保健施設(老健)

「老健」と呼ばれることもある施設です。病気や怪我などで心身機能が低下した方に対して、看護や医学的管理をしながら介護・リハビリなどを行うことにより、在宅復帰するまでの生活を支援する施設です。在宅介護を受けている方だけでなく、退院直後のため集中的なリハビリが必要な場合も対象になります。
個室を設ける施設は少なく、多床室がメインとなるのが特徴です。
入居条件・入居対象者
対象となるのは要介護度1以上で、病状が安定して入院治療が必要ない高齢者です。あくまでも在宅復帰を目標とする施設のため、入居期間は原則3~6か月と定められています。
実際には期限がきても身体状況が回復していなかったり、在宅介護の体制が整っていなかったりして入居期間が長期にわたることもあります。そのため、施設の利用率も90%と高く、入居は難しい現状にあります。
老健はリハビリが充実している
リハビリを行って早期の在宅復帰を目指す施設であること、運営主体が医療法人などであることから、介護職員以外にもリハビリテーションの専門家である作業療法士、理学療法士、言語聴覚士などが複数配置されています。医師と看護師が常駐し看護師の夜勤もあるので、医療面は手厚く安心です。リハビリを終えて在宅復帰が可能と判断された場合は、自宅に戻り、在宅サービスを受けることになります。
介護療養型医療施設(介護療養病床)

地方公共団体または医療法人が主な設置主体で、医療が必要な要介護高齢者のための療養型施設です。後に解説する「介護医療院」の登場により2012年以降は新設されておらず、2024年3月までに全て介護医療院へ転換される予定となっています。
入居条件・入居対象者
病院または診療所としての機能が整っており、介護保険施設でありながら医療機関としての側面もあります。対象となるのは医学的管理が必要な要介護1以上の高齢者のほか、比較的状態が安定している方です。例え要介護1以上の認定がついていても、医療の必要性が高くない場合は現実的に入居困難です。
医療的ケアや機能訓練が充実している
基本的な介護サービスのほか、痰吸引や経管栄養、酸素吸入や人工呼吸器などを使っている方達のように、継続的な医療ケアを必要としている方に対応しています。医療機関として位置づけられる施設のため医療的ケアや機能訓練が充実しており、24時間安心して暮らすことが出来る環境が整っています。
一方、特別養護老人ホームのように、掃除や洗濯、レクリエーションといった生活支援系のケアはあまり提供されていません。身体状況が改善すると退所を求められることもあります。
介護医療院

前述した3つの介護保険施設に、2018年4月から新たに加えられた施設です。長期的な医療と介護のニーズを合わせ持つ、要介護高齢者を対象としています。
要介護高齢者に対し、長期療養のための医療と介護を一体的に提供することを目的としています。介護療養型医療施設が医療機関としての役割を担うのに比べ、介護医療院は「生活の場所」を意識した施設となります。
入居条件・入居対象者
要介護度1から入居対象となるものの、施設の目的を考えると介護度の高い方ほど入居しやすい傾向にあるといえるでしょう。また、医療的ケアの必要性が高い方でも問題なく入居できます。
医療と日常生活の支援(介護)を一体的に提供する
長期療養のための医療や日常的な医学管理が必要な重介護者を受け入れ、医療機能と日常生活の支援(介護)を一体的に提供できるところが特徴です。
医師・看護師・薬剤師をはじめとし、病院や診療所と同様の職員配置になっているため、充実した医療的ケアを受けられます。痰吸引や経管栄養といったケアのほか、緊急時にも対応できます。ターミナルケア(終末期医療)と看取り介護にも対応しているため、終の棲家として選択する道もあるでしょう。
居室はパーテーションや家具で仕切られており、プライバシーに配慮されています。また、1人当たりの面積が介護療養型医療施設(6.4㎡以上)よりも広く設計されている(8㎡以上)ため、より快適に生活を送ることができます。
介護保険施設の費用
| 施設名 | 初期費用(入居金) | 月額費用の目安 |
| 特別養護老人ホーム(特養) | 不要 | 約8万~13万円 |
| 介護老人保健施設(老健) | 不要 | 約6万~16万円 |
| 介護療養型医療施設 | 不要 | 約6万~17万円 |
| 介護医療院 | 不要 | 約7万~17万円 |
介護保険施設に関する費用の中で共通した特徴は、以下の2つです。
- ・初期費用(入居一時金・権利金・敷金礼金など)が不要なこと
- ・月額費用の助成を受けられる可能性があること
介護保険施設は公的な費用助成制度の対象となっており、入居する方の収入や財産に応じてサービス利用料や介護保険給付対象外である食費・居住費の一部に助成を受けることができます。
特定入居者介護サービス費(負担限度額認定制度)
対象者の収入や貯蓄が条件に合致する場合に介護保険施設入所時の食費や居住費を助成する制度です。主に生活保護の方や住民税非課税の方が対象です。この助成を受けるためには、市区町村に申請する必要があります。
【対象者】
| 助成段階 | 条件① 収入の状況 | 条件② 預貯金額の状況 |
| 第1段階 | 生活保護受給者 | なし |
| 世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者 | 1,000万円(夫婦の場合2,000万円) | |
| 第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額が80万円以下 | 650万円(夫婦の場合1,650万円) |
| 第3段階① | 世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額が80万円超~120万円以下 | 550万円(夫婦の場合1,550万円) |
| 第3段階② | 世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額が120万円超 | 500万円(夫婦の場合1,500万円) |
| 第4段階 | 住民税課税対象者がいる世帯 |
【助成額① 特別養護老人ホームの場合】(日額)
| 基準額 | 負担限度額 | |||||
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | |||
| 食費 | 1,445円 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 | |
| 居住費 | 従来型個室 | 1,171円 | 320円 | 420円 | 820円 | 820円 |
| 多床室 | 885円 | 0円 | 370円 | 370円 | 370円 | |
| ユニット型個室 | 2,006円 | 820円 | 820円 | 1,310円 | 1,310円 | |
| ユニット型室的多床室 | 1,668円 | 490円 | 490円 | 1,310円 | 1,310円 | |
【助成額② 介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院の場合】(日額)
| 基準額 | 負担限度額 | |||||
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | |||
| 食費 | 1,445円 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 | |
| 居住費 | 従来型個室 | 1,668円 | 490円 | 490円 | 1,310円 | 1,310円 |
| 多床室 | 377円 | 0円 | 370円 | 370円 | 370円 | |
| ユニット型個室 | 2,006円 | 820円 | 820円 | 1,310円 | 1,310円 | |
| ユニット型室的多床室 | 1,668円 | 490円 | 490円 | 1,310円 | 1,310円 | |
住民税が非課税の世帯であれば、上記いずれかの対象となる可能性が高いです。同居している家族が課税対象者であっても、世帯分離によって別世帯となっている場合はこの制度の対象になる場合もあります。まずは市区町村の担当窓口に問い合わせてみましょう。
・厚生労働省. 「サービスにかかる利用料」.https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html, (参照 2023-03-15)
住民税課税層に対する食費・居住費の特例減額措置
課税世帯であるがゆえに上記の「特定入所者介護サービス費」の対象にはならなくても利用できる可能性がある助成制度です。以下すべての条件に当てはまる場合に特例的に「特定入所者介護サービス費」の第3段階②に相当するとして同等の助成を受けられる制度です。
- 1.世帯の構成員が2人以上であること。(配偶者が世帯分離している場合や、施設入所によって別世帯となった場合も同一世帯とみなす)
- 2.介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設(通称:ミニ特養)に入所し、第4段階の食費・居住費の負担を行うこと
- 3.世帯主および世帯構成員ならびに配偶者の年間収入から、施設の利用者負担の年間見込み額を除いた金額が80万円/年以下となること。
- 4.世帯主および世帯構成員ならびに配偶者の現金・預貯金などの額が450万円以下であること。※有価証券、債券なども含む
- 5.世帯主および世帯構成員ならびに配偶者が住居としている家屋その他日常生活上必要な資産以外に利用できる資産がないこと
- 6.介護保険料を滞納していないこと
この制度も、利用するためには市区町村に申請する必要があります。
・茅ヶ崎市. 「住民税課税層に対する食費・居住費(滞在費)の特例減額措置について」.https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/otoshiyori/riyosyafutan/1004186/1004190.html, (参照 2023-03-15)
社会福祉法人等による低所得者に対する利用者負担額軽減制度
低所得で特に生活が困難な方の介護保険サービス利用を促進することで生活を支援する制度です。社会福祉法人の社会的な責務として、提供したサービスを利用した方の自己負担額のうち25%を減免します。対象になる運営主体が社会福祉法人であるため、介護保険入所施設の中では特別養護老人ホームとミニ特養が対象になります。
助成の対象になるためには、次の要件を全て満たす必要があります。
- ・住民税非課税世帯であること
- ・年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
- ・預貯金などの額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
- ・日常生活に必要な資産以外に活用できる資産がないこと
- ・負担能力のある親族などに扶養されていないこと
- ・介護保険料を滞納していないこと
この制度も上記の2種類の制度と同様に、利用するためには市区町村に申請する必要があります。
施設選びに悩んだら介護の広場に相談してみよう

介護保険施設は、それぞれに要介護高齢者の生活を支える役割を担っています。施設選びの際は違いや目的見極めることが大切です。以上の4つの施設内容を知ったうえで、担当ケアマネジャーや介護保険施設の担当者と相談しながら、本人にとって最適な施設を見つけましょう。
また、なかなか直接近所の施設に相談に行くことは「気が引ける」「恥ずかしい」とお考えの方には、日常的な介護の困りごとをQ&A方式で質問できる「介護の広場」がおすすめです。介護のお悩みを投稿するだけで、介護経験のあるかたや専門職から回答を得ることができます。ぜひ一度アクセスしてみてください。
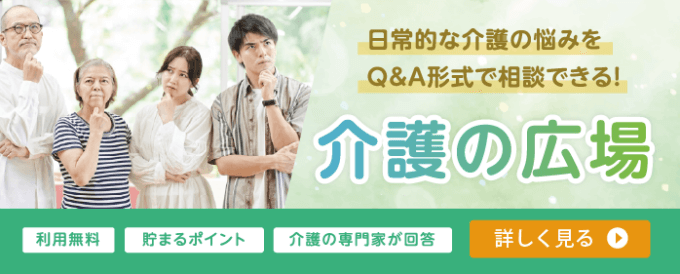
「介護保険施設とは?4施設のサービス内容や費用の違いを解説」に関連する記事
多くの介護事業所の管理者を歴任。小規模多機能・夜間対応型訪問介護などの立ち上げに携わり、特定施設やサ高住の施設長も務めた。社会保険労務士試験にも合格し、介護保険をはじめ社会保険全般に専門知識を有する。現在は、介護保険のコンプライアンス部門の責任者として、活躍中。